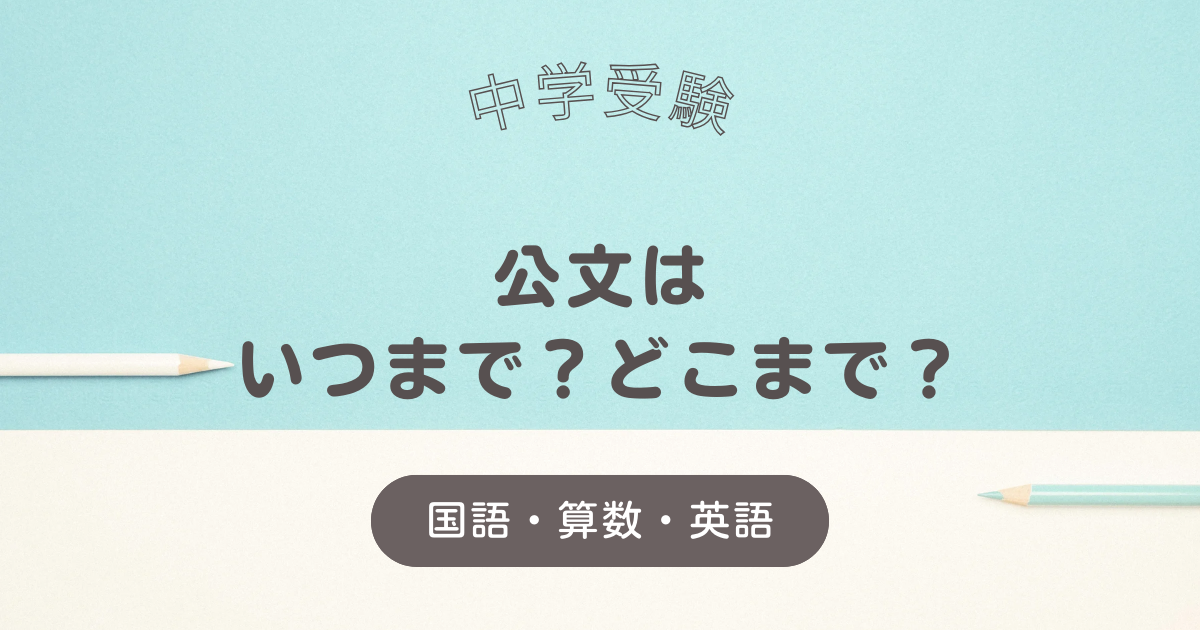
通塾前の公文
中学受験をする予定のご家庭では、通塾前に公文に通って先取りをしておくことがスタンダードとなって久しいですね。
わが家の娘も、年長の終りから通って約1年で算数F・国語D・英語Gに到達しました。
1年で辞めた理由はいろいろあります。
- 高進度になってしまって本人が負担に感じるようになったこと。
- 一番の目標だった算数Fを達成できたこと。
- 上の子の受検で手一杯になり、くもんの送り迎えや宿題の管理が難しくなったこと。
- 月謝が高すぎるのが気になっていたこと。
当時はやめるのが最善だったけれど、もう少し続けていれば良かったなーと思うこともあります。
ではいったい、いつまで、どこまで続けるのが良かったのか、その後の娘の学習・成績をふまえて考えてみたいと思います。
公文はすごい!
わたしは公文肯定派です。公文はすごいですよ。
電車でいえば、家庭学習が各駅停車で公文は急行。自転車でいえば公文は電動自転車。
子どもの機嫌を取りながら一歩一歩進める動力源を、肩代わりしてくれるイメージです。
唯一の欠点は月謝が高すぎる(1科目8,000円!)ことですが、それさえも、公文を神聖化し、必ず宿題をさせるという親の気迫を生み出す源となっているような気がします。
それでは、中学受験をするという前提のもと、いつまでにどこまで進めるのが良いのか科目ごとに検討してみましょう。
算数
公文といえば算数。公文といえば計算。
計算を得意にするために公文を始める方が、最も多いのではないでしょうか。
たし算ひき算から始まり、かけ算わり算、小数、分数と目に見えて進むので、効果がわかりやすいのが算数です。
小学校で習う計算はF教材までなのでFまでで良いという意見も見られますが、わたしはHの連立方程式までやっておくと受験算数の理解が速くなると思います。
なぜなら、連立方程式って中学受験でまんま使うことがあります。
まんじゅう算とか消去算とかですね。つるかめ算も方程式を使えば簡単に解けます。
いまどき、方程式使ったから答えはあってるけど減点、なんていう私立中はないですよね。
算数に関しては、入塾する小3の2月までにH教材までがベストだと思います。
それが無理なら、F教材まででも充分です。
娘は、どんどん進ませてくれる先生だったので1年でFまでいきました。正確に言うと、F50でやめました。(一つの教材は200まであります)
小学生の計算の最後の関門である「分数のかけ算わり算」、通称・約分地獄でリタイアです。
多量の演習はできなかったけれど、やり方だけはマスターしたので良しとしました。
公文をやめてから、
- 計算練習の続き
- 計算以外の小学校算数
- 中学3年までの数学
を、コツコツと勉強しました。
家庭学習になってからも、なんとなく公文の勢いが残っていたから進めたと思います。
親の主導だけで、ここまでさせるのはなかなか。
➡【KUMON小1】算数E終了(102日間)。しかしF50でリタイア!
スポンサーリンク
国語
国語は一つの教材がⅠとⅡにわかれて合計400枚あるので、算数英語と比べてどうしても進みは遅くなります。
娘が進んだD教材は小学4年生レベルです。
国語の教材はAからFまでほぼ同じような構成で、読解・文法・漢字の問題をバランスよく解いてくことになります。
読解問題は、文章を読んで聞かれたことの答えを"探す"作業のくり返しで、簡単といえば簡単なのですがこれがものすごくじわじわと効くのです。
長文読解が苦手な子は、答えを自分で考えようとする傾向があります。
国語の問題は、考えるのではなく文章中から「探す」が正解ですね。
そのことを、自然に体に染み込ませてくれるのが公文国語です。
娘は公文国語の効果がまだ続いていた低学年のころ、国語はいつもほぼ満点の無双状態でした。
ところが、高学年になっていつの間にやら文章をよく読まなくなり、得意とは言えなくなってきています。
家庭学習でも読解のドリルはしていましたが、公文ほどの効果は出せませんでした。なぜかしら。
間違い直しに対する甘さに、その原因があるように感じます。
国語こそ、感情を排して完璧に論理的にならないといけないのに、国語の丸付けはどうも白黒つけにくく、中途半端にしてしまいがちなんですよね。反省。
G教材以上になると「要約」の練習もできるようで、これもぜひ、やっておきたかったですね。今からでも遅くない?
公文国語は、いつまでにどこまでというのはないけれども、出来る限り続ける価値のあるものだと思います。
英語
英語は、基本的に中学受験とは関係ありません。
ただ、大学受験までも視野に入れた学習計画を考えたときに、低学年での英語学習はやっておいた方がベターです。
英語の教材は中学範囲であるG教材からが本番で、F教材までは"英語慣れ"のためのお遊びのようなものです。
コストパフォーマンスを考えると、アルファベットや簡単な英単語は家庭学習で済ませておいて、なるべく早くG教材に到達できるようにすることをおすすめします。
どこまで進めばよいかというのは、英検何級まで取っておきたいかによりますが、目標が4級ならH教材まで、3級ならI教材までということになります。
ちなみに、公文英語だけで英検に合格できるわけではありません。
過去問その他、家庭で補わなければならないところはけっこうあるということは、知っておいた方が良いかもしれません。
公文ができる子は強い!
公文は、週2回も通わないといけない上に、毎日大量の宿題をこなさなくてはならないという大変ハードな習い事です。
1科目ならまだしも2科目以上となると、低学年から毎日1時間以上の学習習慣がつけられることになります。これは、誰にでもできることではありません。
つまり、公文を嫌がらずにきちんとこなせる子どもは、間違いなくコツコツタイプ。
中学受験のための通塾が始まっても、パンクせずに努力を続けられる資質があります。
わが家においても、真ん中の娘だけは公文を嗜むことができましたが、あとの2名は
- 人から指示されるの大嫌い!
- 毎日同じことの繰り返しなんてお断り!
みたいな感じで公文入会は断念しています。
公文はどこまでやっておけばいいのかしら?なんていう悩みが持てる時点で、そのお子様は充分に優秀でいらっしゃいます。
スポンサーリンク